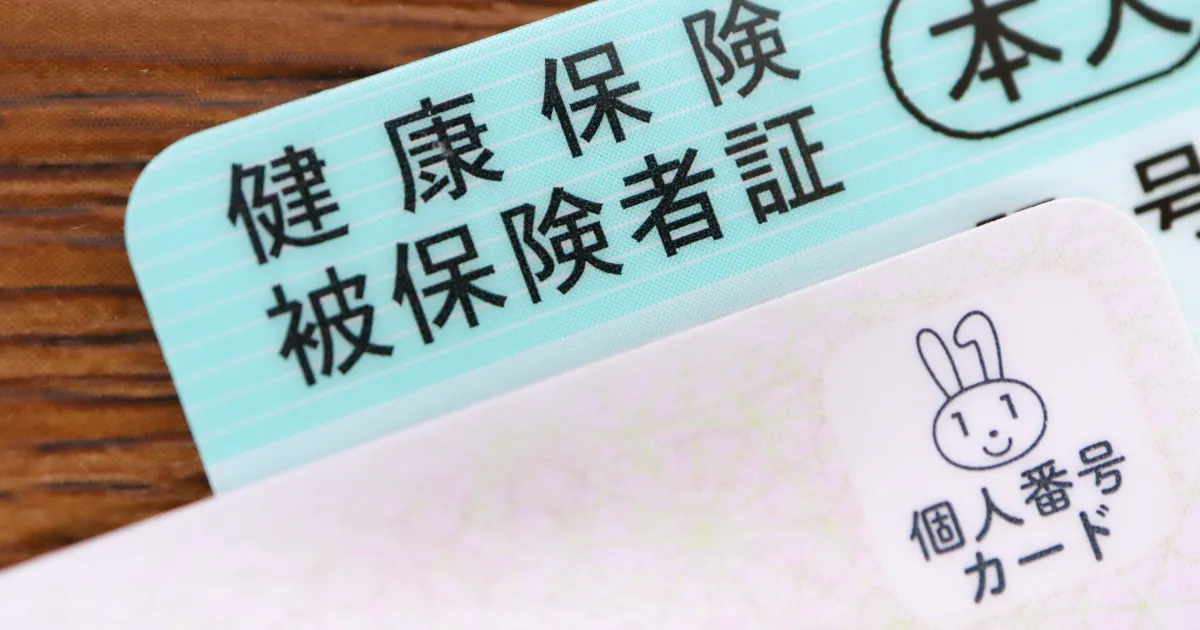国民健康保険葬祭費の概要
国民健康保険葬祭費とは、国民健康保険に加入していた方が亡くなった際に、葬儀を行った方(喪主)に対して支給される給付金です。
この制度は、葬儀費用の負担軽減を目的としており、全国の市区町村で実施されています。申請により一定の金額が支給されるため、忘れずに手続きを行うことが大切です。
支給対象者

被保険者(故人)の条件
- 国民健康保険に加入していた方(原則75歳未満)が亡くなった場合
- 保険料の滞納があっても原則として支給対象
- 他の健康保険から国保に切り替わったばかりでも対象
申請者(受給者)
- 葬儀を行った方(喪主)
- 故人との関係は問わない(家族でなくても可)
- 葬儀費用を実際に負担した方
支給金額
一般的な支給額
- 5万円:多くの自治体で採用
- 3万円:一部の自治体
- 7万円:東京都23区など
地域による違い
| 地域例 | 支給額 |
|---|---|
| 守山市 | 5万円 |
| 野洲市 | 5万円 |
| 栗東市 | 5万円 |
| 草津市 | 5万円 |
| 東京都23区 | 7万円 |
| 横浜市 | 5万円 |
| 大阪市 | 5万円 |
| 名古屋市 | 5万円 |
| 福岡市 | 3万円 |
※2025年8月5日現在の情報です。詳細は各自治体にご確認ください。
他制度との関係と注意事項
重複受給はできません
以下の給付金はどれか一つのみ受給可能です。複数受給することはできません。
1. 国民健康保険葬祭費(本記事の制度)
- 対象:国民健康保険加入者(75歳未満)
- 支給額:3〜7万円(自治体により異なる)
2. 後期高齢者医療葬祭費
- 対象:後期高齢者医療制度加入者(75歳以上)
- 支給額:多くの自治体で5万円
- 申請先:同じ市区町村の窓口
3. 社会保険の埋葬料・埋葬費
- 対象:健康保険組合・協会けんぽ等の加入者
- 支給額:5万円(一律)
- 申請先:各健康保険組合・協会けんぽ
制度選択の判断基準
- 故人が複数の保険に加入資格がある場合、支給額を比較して有利な方を選択
- 一度申請すると他制度は利用不可のため、事前確認が重要
申請に必要な書類
基本的な必要書類
- 葬祭費支給申請書(市区町村の窓口で入手)
- 故人の国民健康保険証
- 死亡診断書または死体検案書(コピー可)
- 葬儀の領収書または会葬礼状
- 申請者(喪主)の身分証明書
- 申請者の口座情報(通帳など)
自治体によって追加で必要な場合
- 戸籍謄本
- 住民票
- 印鑑(認印可)
申請方法と流れ

申請場所
- 故人が住んでいた市区町村の国民健康保険担当窓口
- 守山市:国保年金課
- 野洲市:保険年金課
- 栗東市:保険年金課
- 草津市:保険年金課
- その他自治体:市民課・保険年金課など(自治体により名称が異なります)
申請の手順
1. 書類の準備
- 必要書類を事前に確認・準備
2. 窓口での申請
- 平日の開庁時間内に窓口で手続き
- 一部自治体では郵送申請も可能
3. 審査・支給
- 申請から約2〜4週間で指定口座に振込
- 支給決定通知書が郵送される
申請期限
- 葬儀を行った日から2年以内
- 期限を過ぎると支給されないため注意が必要
注意点とポイント
間違いやすいポイント
- 故人の住所地で申請しましょう(本籍地では申請できない)
- 葬儀を行った方が申請しましょう(故人の配偶者とは限らない)
- 申請期限は葬祭を行った日の翌日から2年です(死亡日ではない)
申請時のコツ
- 葬儀社に制度について相談
- 必要書類は葬儀社でも案内してもらえることが多い
- 不明な点は事前に市区町村に電話確認
各制度の比較表
| 項目 | 国保葬祭費 | 後期高齢者医療葬祭費 | 社保埋葬料・埋葬費 |
|---|---|---|---|
| 対象年齢 | 原則75歳未満 | 75歳以上 | 年齢制限なし |
| 支給額 | 3〜7万円 | 多くは5万円 | 5万円 |
| 申請先 | 市区町村 | 市区町村 | 健康保険組合等 |
| 申請期限 | 葬祭日の翌日から2年 | 葬祭日の翌日から2年 | 死亡日から2年 |
| 申請者 | 葬儀を行った方 | 葬儀を行った方 | 被保険者の家族等 |
よくある質問
Q. 保険料を滞納していても支給されますか?
A. 原則として支給されます。ただし、自治体によっては制限がある場合もあります。
Q. 故人が他県に住んでいた場合はどこで申請しますか?
A. 故人が最後に住んでいた市区町村で申請します。
Q. 葬儀をしなかった場合(直葬のみ)でも支給されますか?
A. 火葬のみでも支給対象となります。自治体により「火葬料」などの名目の場合もあります。
Q. 申請を忘れていた場合はどうすればいいですか?
A. 2年以内であれば申請可能です。すぐに市区町村の窓口に相談してください。
Q. 葬儀費用が支給額より少ない場合はどうなりますか?
A. 実際の葬儀費用に関係なく、規定の金額が支給されます。
まとめ
国民健康保険葬祭費は、葬儀費用の負担を軽減する重要な制度です。支給額は決して大きくありませんが、確実に受け取れる給付金ですので、忘れずに申請しましょう。
特に重要なのは、他制度との重複受給はできないことです。故人の加入していた保険制度を確認し、最も有利な制度を選択してください。
申請手続きは比較的簡単ですが、期限や必要書類は自治体によって異なる場合があります。事前に確認し、適切な時期に手続きを行うことが大切です。
悲しみの中での手続きは大変ですが、故人が長年加入していた制度からの最後の給付として、ぜひご活用ください。
※支給額や申請方法は自治体によって異なります。詳細は故人の住所地の市区町村にご確認ください。
関連記事
準備中