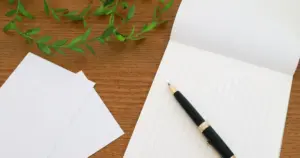葬儀での挨拶は、故人への感謝と参列者への感謝の気持ちを伝える大切な場面です。長い挨拶は必要ありません。心からの感謝の気持ちを簡潔に、丁寧に伝えることが最も重要です。
地域の慣習や家族の方針によって挨拶の内容は変わることもあります。以下のポイントを参考に、ご自身の言葉で心を込めて挨拶されることをお勧めします。
挨拶の基本構成
感謝の表現から始める
挨拶の冒頭では、参列への感謝を込めて「お忙しい中お越しいただき」「足元の悪い中」といった言葉で始めます。続いて生前のお世話への感謝として「生前は大変お世話になりました」と述べ、温かいお心遣いへの感謝も忘れずに伝えましょう。
この感謝の表現は、故人に代わって遺族が心からお礼を申し上げる大切な瞬間です。
故人について触れる
故人の人柄や性格について簡潔に触れることで、参列者との共通の思い出を呼び起こします。故人と参列者の関係でお世話になったことや思い出があれば、それに言及することも効果的です。
「故人も喜んでいることと思います」という言葉で、故人の気持ちを代弁することで、温かい雰囲気を作ることができます。
今後のお願いで締めくくる
挨拶の最後は、「今後ともよろしくお願いいたします」という変わらぬお付き合いへのお願いや、「ご指導のほどよろしくお願いいたします」というご指導への願い、そして「故人の教えを胸に精進してまいります」という決意を述べて締めくくります。
個別のお礼の言葉
基本的なお礼の表現
日常的な場面では「本日はお忙しい中、ありがとうございました」という一般的な表現が適切です。より丁寧に表現したい場合は「お疲れのところ恐れ入ります。ありがとうございます」と述べ、感謝を強調したい時は「お心遣いをいただき、ありがとうございます」という表現を使います。
香典・供花への心のこもった対応
香典を受領する際は「ご丁寧にありがとうございます」「恐れ入ります」と述べ、供花や供物をいただいた場合は「お心遣いをいただき、恐縮です」と感謝を表現します。弔電については「ご丁寧なお心遣いをありがとうございます」と、送っていただいた気持ちに対する感謝を伝えましょう。
関係性に応じた心配り
職場関係の方には「生前は大変お世話になりました」と仕事上でのお世話への感謝を、ご近所の方には「いつもお世話になっております」と日頃の関係への感謝を表現します。友人・知人には「遠いところありがとうございます」と、遠方の方には「遠路はるばるありがとうございます」と、足を運んでいただいた労をねぎらいます。
避けるべき言葉への注意
忌み言葉への配慮
「重ね重ね」「たびたび」「いよいよ」「ますます」「くれぐれも」などの重ね言葉は、不幸が重なることを連想させるため避けます。また「再び」「再度」「また」「続く」「追って」などの繰り返しを意味する言葉も同様に使用を控えましょう。
直接的な表現の言い換え
「死ぬ」「死亡」「生きていた頃」などの直接的な表現は避け、「亡くなる」「永眠」「旅立つ」「生前」といった婉曲的な表現を使用します。これにより、より品位のある挨拶となります。
宗教的配慮の重要性
仏教以外の葬儀では「成仏」「供養」「冥福」などの仏教用語に注意が必要です。無宗教の場合は宗教的な表現は避け、神道の場合は「安らかにお眠りください」ではなく「安らかにお鎮まりください」を使用します。
挨拶の心構えと準備

話し方のポイント
挨拶では聞き取りやすいようゆっくりと明瞭に話し、会場の大きさに応じて声量を調整します。心からの感謝の気持ちを込めて、慌てず落ち着いた口調で話すことが大切です。
時間の目安は3〜5分程度とし、感謝の気持ちを中心に故人の人柄や思い出を交えながら要点を絞って話します。感情的になってしまった場合は無理に続けず、一呼吸置くことも必要です。
表情と態度への配慮
悲しみを表しながらも品位を保った落ち着いた表情を心がけ、正しい姿勢で相手と向き合います。常に参列者の気持ちや状況に配慮した態度で接することが重要です。
事前準備の大切さ
大切なポイントはメモしておき、事前に声に出して練習しておくと安心です。体調や精神状態により、代役を立てることも考慮し、挨拶の内容について家族と相談しておくことも重要です。
当日は完璧な挨拶を目指す必要はなく、例文を参考にしながらも自分の言葉で表現し、技術よりも心からの感謝を大切にします。体調や精神状態に応じて柔軟に対応することも必要です。
家族葬での特別な配慮
アットホームな雰囲気作り
家族葬では少人数での温かい雰囲気を大切にし、一人ひとりとの時間を大切にできるという特徴を活かします。厳格な形式よりも心のこもった対応を重視しましょう。
家族葬での挨拶では「家族だけの小さな葬儀ですが」という温かみのある表現を使い、「こうしてお越しいただき」と感謝の気持ちを強調します。個人的なエピソードを交えることで、故人との関係をより大切に表現できます。
特別な状況での配慮
若い方が亡くなった場合
若い方の葬儀では「短い人生でしたが」と短い人生への言及をしつつ、「多くの方々に愛され、支えられました」と多くの愛への感謝を表現します。若い命を失った悲しみを共有しながら、その人が多くの人に愛されていたことを伝えることが大切です。
長寿の方が亡くなった場合
長寿を全うされた方の場合は「○○歳の長い人生を」と長い人生への感謝を述べ、「最後まで温かく見守っていただき」と見守りへの感謝を表現します。人生を全うした満足感と、支えてくださった方々への感謝を込めて伝えましょう。
闘病生活があった場合
長い闘病生活があった場合は「長い間の闘病生活でしたが」と闘病への理解を示し、「最後まで励ましていただき」と励ましへの感謝を表現します。病気と向き合った故人の姿勢と、支えてくださった方々への感謝を込めて伝えることが重要です。
まとめ
葬儀での挨拶は、故人への最後のお礼と、参列者への感謝を伝える大切な機会です。完璧な挨拶を目指す必要はありません。心からの感謝の気持ちを、ご自身の言葉で素直に表現することが最も重要です。
悲しみの中での挨拶は大変ですが、故人を偲んでお越しいただいた方々への感謝の気持ちを込めて、温かい言葉でお礼を伝えましょう。家族や親族と相談しながら、無理のない範囲で心のこもった挨拶を心がけてください。
※地域や宗派によって慣習が異なる場合があります。詳細は地域の年配者や葬儀社にご相談ください。
関連記事